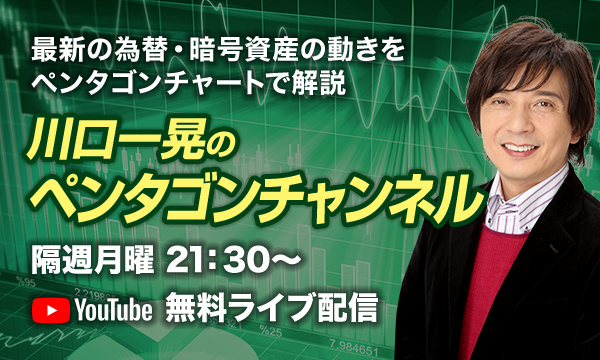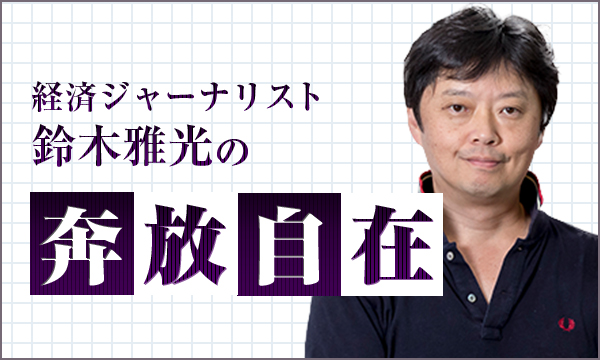金利を知ろう
> 無料のFX口座開設でお肉・お米のいずれかゲット!

バブル崩壊後の1999年から始まった日本の超低金利政策は、実に四半世紀もの間続いてきました。その結果、30代の若者には「年1~2%」でも高金利と感じる世代が育ち、消費行動にも影響を与えています。金利正常化時代の資産運用と借入の心得を解説します。
日本が、いわゆる「ゼロ金利政策」を取ったのは、1999年2月のことでした。この時、日本銀行は政策金利である無担保コール翌日物金利を、史上最低の0.15%に誘導することを決めたのです。当時の速水日銀総裁が「ゼロでも良い」と発言したことから、「ゼロ金利政策」と言われるようになったのですが、この時は早期のうちにゼロ金利政策の解除を目指す方針を示していました。
その後、2000年のITバブル、2006年の景気回復によって解除を試みたものの、その後の景気低迷によって再びゼロ金利を導入する、ということを繰り返し、2013年4月からの黒田日銀総裁の時代に「黒田バズーカ」が炸裂し、2016年1月29日には「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」が導入され、マイナス金利が続きました。
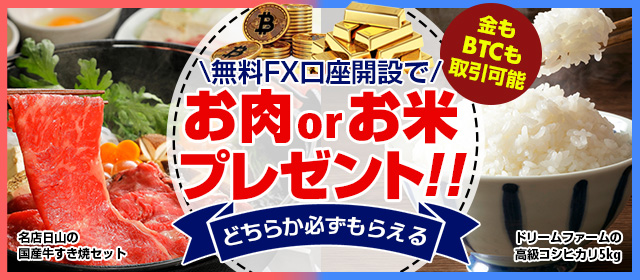

2024年3月19日、植田日銀総裁のもと、無担保コール翌日物金利の誘導目標を0.0%~0.1%程度とすることにして、ようやくマイナス金利政策が解除され、ゼロ金利政策に復帰。さらに2024年7月31日には、無担保コール翌日物金利の誘導目標を0.25%程度とし、2025年1月からは0.5%程度へと引き上げられ、ようやくプラス金利になりました。徐々にですが、金利は正常化に向けて動き始めたのです。
このような「ゼロ金利政策→マイナス金利政策→ゼロ金利政策→金利正常化」の道筋を追ってみると、非常に長いこと超低金利が続いたことが分かります。途中、ゼロ金利政策を解除する動きがあったとはいえ、日本がゼロ金利政策に突入したのが1999年2月ですから、2024年7月にプラス金利へと復帰したところまでの時間は、24年と5カ月もかかったのです。
ということは、前出の30歳の記者にとっては、5歳だった頃からずっと金利がほとんどない世界で生活してきたので、年1~2%の金利でも「高い」と思うのは、自然なのかも知れません。
ただ、それを聞いて1つだけ、少し不安になったことがあります。昔はもっと金利水準が高く、ローンの金利は5~6%が普通でしたし、それでも個人消費は旺盛でした。ところが、1~2%でも高金利と思ってしまう人が、30代を中心にして結構な割合でいるのだとしたら、個人消費など当分の間、盛り上がることはないのではと思ったのです。しかも、この世代は老後に対する不安も抱えている世代です。そのうえ金利が1~2%どころか、3%、4%、5%というように上昇していったら、ローンを組むことが必要な大型消費には手を出さなくなるかも知れません。それはとりもなおさず、日本の消費意欲が落ちていくことを意味します。
とはいえ、金利上昇を不安視してばかりいても、何も始まりません。大事なのは今後、金利が上昇していくとして、何をする必要があるのか、何をしない方が良いのかを、整理しておくことです。
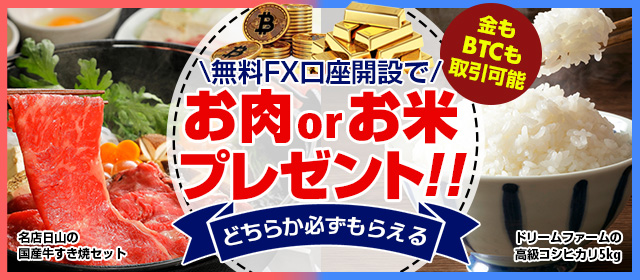

金利上昇局面で有利なのは、まず預貯金による運用です。一般的に金利上昇局面では、預入期間が短い預貯金の利率に比べ、長い預貯金の利率の方が高く設定されます。利率だけを見れば預入期間の長い預貯金が有利に見えますが、金利が上昇し始めた時に、預入期間10年の預貯金で運用すると、満期を迎えるまでの間に複数回あると思われる高金利のメリットを享受できません。
したがって、金利上昇のピッチが速い時は、満期までの期間が1年、もしくは6カ月程度の預貯金に預け、満期日を迎えた時に、新しい利率で同期間の預貯金に乗り換える自動継続にします。
また、変動金利型の金融商品で、10年物の個人向け国債も金利上昇メリットを享受できます。半年おきに適用される利率が見直されるので、金利上昇局面ではその都度、適用利率が引き上げられるのです。
ただし債券でも、利率が償還まで変わらない固定金利型の債券で、償還までの期間が5年、10年と長いものは、金利が上昇している途中で売却すると、債券価格が額面よりも値下がりしていて、損失を被る恐れが生じてきます。固定金利型の債券での運用は、避けた方が良いでしょう。
一方、金利上昇局面で不利になるのは借入です。個人が行う借入といえば住宅ローンが挙げられますが、住宅ローンの金利は変動金利型と固定金利型とに分かれます。
金利が上昇局面にある時は全期間固定金利、もしくは固定金利適用期間ができるだけ長い住宅ローンを組んだ方が、完済するまでに金利が上昇しても、返済負担が増えずに済みます。
ちなみに個人の借入には、クレジットカードのキャッシングや消費者ローンもありますが、これらは高金利であるかどうかに関係なく、常時、それ相応に高い利率で返済額が計算されますから、あまり多用しないことをお勧めします。

鈴木雅光(すずき・まさみつ)
金融ジャーナリスト
JOYnt代表。岡三証券、公社債新聞社、金融データシステムを経て独立し(有)JOYnt設立し代表に。雑誌への寄稿、単行本執筆のほか、投資信託、経済マーケットを中心に幅広くプロデュース業を展開。
> 無料のFX口座開設でお肉・お米のいずれかゲット!